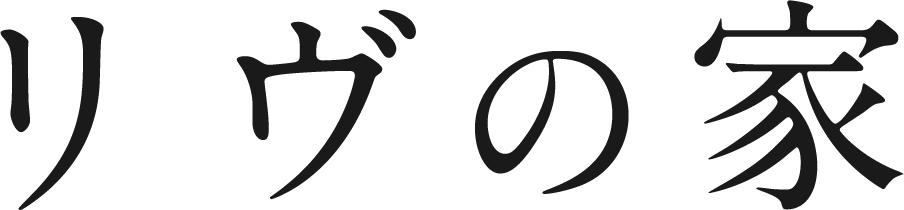こんにちは。設計の奥田です。
今日は「家相」について、少し整理してみたいと思います。
家づくりの打ち合わせの中で、ときどき出てくるこの質問。
「これって、家相的にダメなんですかね?」
多くの場合、ご本人より、ご両親やご親戚が気にされていて、でもなぜダメなのかは分からないまま話が進む、ということがあります。
僕自身も「なんとなく避けるもの」という印象しかなかったので、一度きちんと調べてみました。今回はその内容を共有します。
建築家・清家清さんが書かれた『家相の科学』という本では、家相を次の3つに分類しています。
①建築計画上、合理的な知恵(風通し、採光、動線など)
②当時の生活習慣や道徳に基づく考え
③信仰やただの迷信
つまり、家相は単なる迷信ではなく、昔の合理性が形になったルールを含んでいる、ということです。
そもそも、家相の多くは江戸時代中期以降の「家相書」に由来します。
当時の家は木・土・紙でできており、トイレは汲み取り式、台所は煙や臭いが強く、風通しと日当たりが快適性を左右していました。
換気扇も断熱もない時代に「この方角にこれがあると不便だった」という経験知が家相として整理されていった、とのことです。
では、家相の話でよく出てくる「鬼門」「裏鬼門」について以下にまとめてみます。
「鬼門(北東)」と「裏鬼門(南西)」を避けるべきとされた背景には、気候・建材・町のつくりという、当時の環境条件が関係しています。
北東(鬼門)は、冬に冷風が入り込み、日当たりが乏しい。紙や土でできた江戸時代の家では、結露や湿気、カビが発生しやすい、衛生上良くない場所でした。
南西(裏鬼門)は、西日で室温が急上昇し、食品が傷みやすい。さらに風上にあたり、かまどの煙や臭いが家全体に回りやすく、乾いた風が火の粉をあおることで、火災の延焼リスクも高かったとされています。
つまり、北東は“湿気と寒さの温床”、南西は“熱と火のリスク地帯”だったということです。
こうした背景をふまえると、家相でよく話題になるNG間取りも、「昔は確かにリスクがあった」ものが多いとわかります。
【キッチンが鬼門・裏鬼門にあるのはNG】
江戸時代においては煙やにおい、火災リスクの高い場所だったため、配置に注意が必要でした。冷蔵庫がないため食品が傷みやすくもありました。
でも今は冷蔵庫ありますよね。換気扇は必ずついており、煙やにおいのコントロールが可能であるため江戸時代の観点から考えると問題ありません。
【トイレが鬼門・裏鬼門にあるのはNG】
汲み取り式だった頃は、においや湿気が問題でしたが、今は基本的には水洗ですし、換気扇はついており清掃性が確保されています。
【家の中心に階段や廊下にあるのはNG】
「中心は空けるべき」は通風・採光の観点からの知恵。今はリビングにスケルトン階段など、開放性を活かした設計が可能です。
家相には当時なりの理由があるのですが、今の住宅では断熱・換気・防火性能が建築基準法で定められており、これをクリアしないと建築ができません。
なので、「昔NGだったこと」が「今は問題ない」ことも多くなっています。
詳細をもっと知りたい方は、建築家・清家清さんの著書『家相の科学』に分かりやすい解説があります。ぜひ一度ご覧ください。
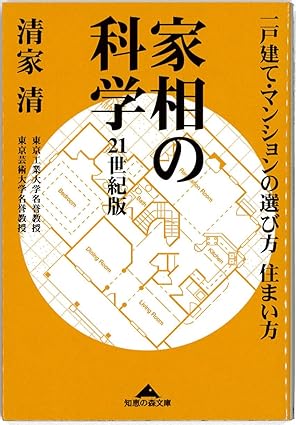
家相の話が出たときは、「信じるか信じないか」というよりも、なぜそのルールが生まれたのかを理解したうえで、今の暮らしに本当に必要かどうかを判断することが大事だと思います。
設計/奥田 渉